
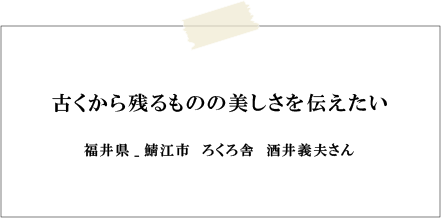
基盤を整えることから
工房へ入って正面の棚には、ろくろで挽いたお椀がびっしりと積み重ねられている。福井県鯖江市の挽物工房〈ろくろ舎〉。主宰の酒井義夫さんは北海道に生まれ、2007年より木工デザイン雑貨のメーカーへの入社を機にこの地へ移り住んだ。退社後、伝統工芸師の清水正義さんに師事し、2014年にろくろ舎を立ち上げる。「お椀はもうあかんわ」。6年前に丸物木地師の師匠の元へ、初めて習いに行った際にいわれた言葉だった。約1500年の歴史を誇る越前漆器の産地、福井県鯖江市。この地で最若手といわれる清水さんでも80歳近い。なぜ今日まで伝統的な技術を受け継いで来られなかったのか。「もう答えは出ていたんですよね。50代60代の職人さんが最初からいなかったわけではなく、廃業してしまったり、辞めて違う職業に就いていたり。学べる場所を作る以前に、まず自分たちの生計が大切ですから」。お椀1個をろくろで挽いても数百円。生計を立てていくとなれば、毎日100個を一年中作らなければいけない。それでどうにか一人が生活していけるくらいであれば、当然人は雇えない。毎日100個という仕事がずっと続くという保証もない。「やり続けてこそ、技術は身に付いてくるもの。でも僕が挽物に集中して、とにかく鍛錬を重ねる状況となれば、確基盤を整えることから100かに上達していくと思うんですけど、新たな職人が出てくるのは難しい。それを続けることに、僕はあまり意味を感じられない。それよりも、次に続く人材が生まれるような環境を作ることの方が優先すべきだと考えていて」



基盤を整えることから
工房へ入って正面の棚には、ろくろで挽いたお椀がびっしりと積み重ねられている。福井県鯖江市の挽物工房〈ろくろ舎〉。主宰の酒井義夫さんは北海道に生まれ、2007年より木工デザイン雑貨のメーカーへの入社を機にこの地へ移り住んだ。退社後、伝統工芸師の清水正義さんに師事し、2014年にろくろ舎を立ち上げる。 「お椀はもうあかんわ」。6年前に丸物木地師の師匠の元へ、初めて習いに行った際にいわれた言葉だった。約1500年の歴史を誇る越前漆器の産地、福井県鯖江市。この地で最若手といわれる清水さんでも80歳近い。なぜ今日まで伝統的な技術を受け継いで来られなかったのか。「もう答えは出ていたんですよね。50代60代の職人さんが最初からいなかったわけではなく、廃業してしまったり、辞めて違う職業に就いていたり。学べる場所を作る以前に、まず自分たちの生計が大切ですから」。お椀1個をろくろで挽いても数百円。生計を立てていくとなれば、毎日100個を一年中作らなければいけない。それでどうにか一人が生活していけるくらいであれば、当然人は雇えない。毎日100個という仕事がずっと続くという保証もない。「やり続けてこそ、技術は身に付いてくるもの。でも僕が挽物に集中して、とにかく鍛錬を重ねる状況となれば、確基盤を整えることから100かに上達していくと思うんですけど、新たな職人が出てくるのは難しい。それを続けることに、僕はあまり意味を感じられない。それよりも、次に続く人材が生まれるような環境を作ることの方が優先すべきだと考えていて」
林業のかたちを考える
「個人的には、お椀は高台がしっかりとある方が好み。ほら、どっしりと構えているようで、オブジェのように置いているだけでも様になるでしょ」。一括りに「お椀」といえど、茶椀、飯椀、汁椀など用途はさまざま。「自分用のお椀を持つという、日本人特有の感覚。毎日の食卓に並ぶお椀がうっとりするような一品だったら…」。そんな思いで、酒井さんは「オンリー椀」と題した漆椀のセミオーダーを始めた。木材、形、漆の塗り方、名入れを自分で選んで注文することができる。「ハゾリ」と呼ぶ型は、唇の形に添わせて縁を反らせているので汁ものが飲みやすい。「ヒョウタン」はくびれがあるので持ちやすく、やわらかな印象。漆の塗り方も、拭き漆や下地から何度も塗り重ねる真塗り、さらに色もぶことができる。それぞれに適した、使いやすい大きさや形を基準に選んでも良い。または、見た目が格好良いという基準だけで選んでも良い。たったひとつの自分用のお椀を持つ手は、きっとこれまでより優しいものだろう。
SHOP DATE
井県鯖江市西袋町512
☎ 0778-42-6523
営業時間:11:00~18:00
定休日:不定休(HP にてご確認ください)
HP:rokurosha.jp











